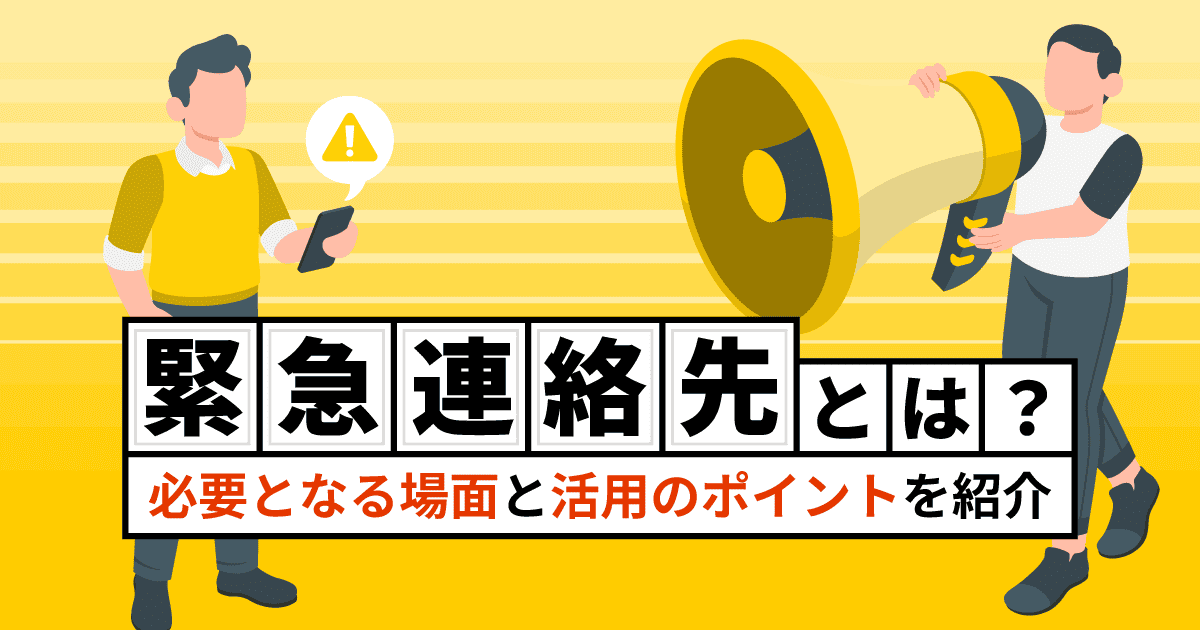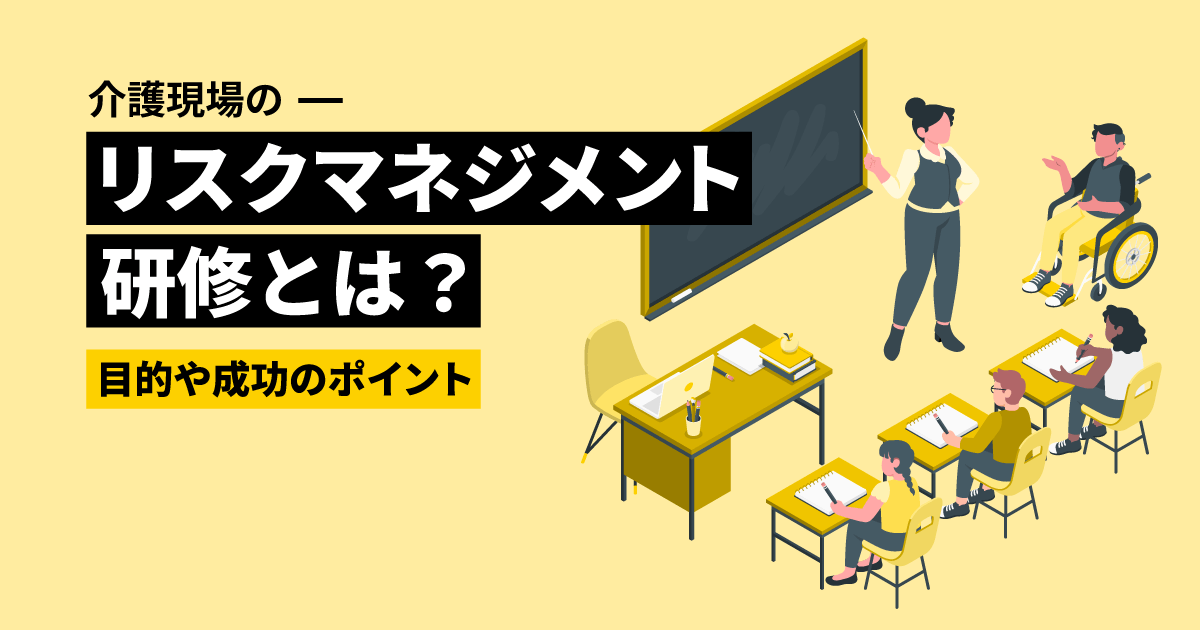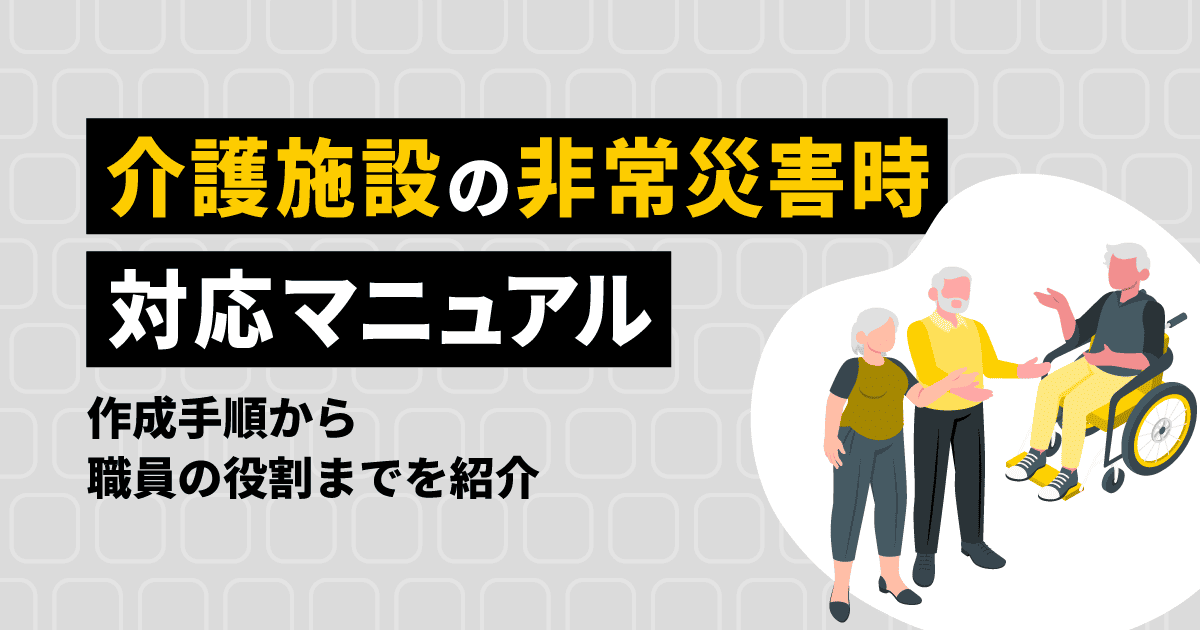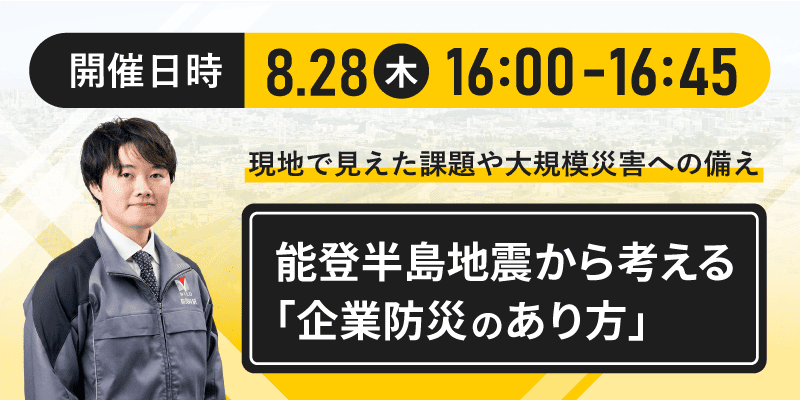医療機関に求められるBCPとは?策定手順と中小病院での対応ポイント
2025/06/25
災害や感染症の拡大など、医療現場には突然の非常事態が訪れます。
そんなときでも診療体制を維持するために欠かせないのが「BCP(事業継続計画)」です。
とはいえ、「うちは小規模だから難しい」と感じる医療機関も多いのではないでしょうか。
この記事では、医療機関におけるBCPの基本と策定手順、中小病院・クリニックでも実践しやすい運用ポイントをわかりやすく解説します。
まずは、自院にできる備えから一緒に考えてみましょう。
医療機関に求められるBCPとは?
医療機関に求められるBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、災害や感染症の拡大といった非常事態が起きた際にも、業務を止めずに継続できるよう備える計画です。医療機関では、この計画が「人命を守る」という使命に直結するため、重要な取り組みとされています。
ここでは、医療機関におけるBCPの役割や対応すべき課題を、次の3つの観点から整理していきます。
それぞれのポイントを踏まえながら、医療現場でBCPがなぜ必要とされるのかを具体的に解説していきます。
BCPの基本と医療機関における役割
医療機関にとってのBCPは、非常時にも診療を継続し、地域住民の命と健康を守るために欠かせない取り組みです。
なぜなら、医療機関は一般企業と異なり「人命を守る」という社会的責任を負っているからです。
電力会社や交通機関などと並び、医療機関は災害時にも止めることが許されないライフラインの一つとされています。診療が滞れば、救えるはずの命が失われる可能性があるため、事業継続の優先度は非常に高いといえます。
例えば、地震によって建物が損傷したり、パンデミックで職員が出勤できなくなったりした場合でも、患者の受け入れ体制や治療体制を維持する必要があります。
そのためには、平時から次のような備えを講じておくことが大切です。
- 指揮命令系統を明確にする
- 必要な医薬品や備品を事前に備蓄する
- 通信手段や電源などの代替手段を確保する
- 非常時のマニュアルや手順を整備する
上記のような準備を通じて、非常時にも慌てずに対応できる体制を築くことが、BCPの基本となります。
医療機関におけるBCPは単なる業務継続ではなく「命を守る医療体制を切らさないための仕組み」であると認識する必要があります。
災害・パンデミック時のリスクと対応
医療機関は、災害や感染症の拡大などの非常時でも、医療提供体制を維持する責任があります。
有事には患者の急増や支援の遅れが発生しやすく、地域の命綱としての機能が一層求められるからです。
平時と異なり、職員の安全確保や資材の確保が困難になることも想定されるため、あらかじめリスクを把握し、対応策を準備しておく必要があります。
例えば、医療機関が直面する主なリスクには以下のようなものがあります。
- 地震・台風・豪雨などによる建物や設備の損傷
- 感染症の流行による職員の出勤困難や院内感染のリスク
- 医薬品・医療資材・食料などの供給停止や在庫不足
- 患者の急増による受け入れ体制の逼迫
リスクに備えるためには、日頃から物資の備蓄や代替手段の検討、職員への情報共有を行い、状況に応じた柔軟な対応体制を構築しておくことが求められます。
有事の際にも地域医療を止めないためには、想定されるリスクを見える化し、具体的なアクションにつなげる準備が不可欠です。
医療施設にBCPは義務化されている?
病院・医療機関のBCP対策は、すべての施設で義務化されているわけではありません。災害時に安定した医療提供を行うために必要な取り組みですが、現時点で法的に義務づけられているのは一部に限られています。
災害拠点病院については、厚生労働省が2017年に定めた「災害拠点病院指定要件の一部改正」により、BCPの策定が義務化されました。
地域の中核医療機関として、地震や大規模災害が発生した際にも、被災者や入院患者への医療提供を継続できる体制づくりが求められています。
一方で、災害拠点病院以外の病院については、BCPの策定は法律上の義務ではなく、あくまで努力義務にとどまっています。
とはいえ、近年の自然災害の激甚化や新型コロナウイルスの流行といったリスクの高まりを受け、策定していない施設は早めの作成がおすすめです。
実際、厚労省が行った「BCPの策定状況等調査(平成30年12月時点)」の結果は、以下のとおりです。

上記のように、BCPはまだ十分に普及しているとは言えない状況です。
現在のところBCPは「義務ではないが、事実上求められている対応」となりつつあります。
すべての医療機関が、いざというときに備えて主体的に整備を進めることが望まれます。
医療機関のBCP策定ステップ
BCPは策定すること自体が目的ではなく、非常時に実際に機能するようにする必要があります。そのためには、計画を現場の状況に落とし込み、スタッフ全体で共有し、定期的に見直すというサイクルが欠かせません。
具体的な流れは、以下のとおりです。
ポイントを一つずつ確認しながら、どのようにBCPを現場レベルに落とし込んでいくべきかを見ていきましょう。
緊急時に備えた役割体制を整える
緊急時の混乱を最小限に抑えるためには、事前に明確な役割体制を整えておく必要があります。
災害やパンデミックなどの非常時には、現場が一気に混乱し、誰が何をすべきか判断がつかなくなることがあります。
混乱を防ぐには、平時のうちに指揮命令系統や各部門の責任者を決め、スタッフごとの役割分担を明文化しておくことが必要です。特に医療機関では、1分1秒の遅れが命に関わるため、迅速かつ的確な対応を実現する仕組みが求められます。
具体的には、以下のような体制づくりが必要です。
- 緊急時に指示を出す責任者を明確にする
- 部門ごとの担当者を決め、役割分担を共有する
- 緊急連絡手段(電話、LINE、安否確認アプリなど)を整備する
- 招集手順や対応フローを文書化しておく
- 実際のシナリオを想定した訓練を行い、実効性を確認する
非常時の備えを通じて、非常時にも現場が落ち着いて機能する体制を構築できます。BCPの第一歩として「誰が、いつ、何をするのか」を明確にしておくことが何より大切です。
施設の防災状況と対応体制を見直す
医療機関が災害時も診療を継続するためには、施設自体の防災性能や非常時の対応体制を定期的に見直しておく必要があります。
災害による建物の損傷や設備の停止は、医療機能の停止に直結します。
特に地震や水害、火災といったリスクは、建物の構造や設備の状態に影響を与えるため、「今ある施設がどれだけ災害に耐えられるか」を把握しなければなりません。
耐久性だけではなく、停電時のバックアップ体制や通信手段の確保も欠かせません。
見直すべき主なポイントは、以下のとおりです。
- 建物の耐震性や火災・浸水への備え
- 非常用電源や通信回線のバックアップ体制
- 医療機器の非常時対応(予備電源・移設計画など)
- 建物全体の診断や安全評価(必要に応じて外部専門家の活用)
上記項目を定期的に点検・確認すれば、実際の災害時にも安心して医療活動を継続できます。「診療の中断を防ぐための防災体制」は、BCPを支える土台とも言えるでしょう。
想定される被害を具体的に洗い出す
有事に備えるためには、まず想定される被害を具体的にイメージし、対応すべきリスクを洗い出しておく必要があります。
災害時に何が起こるかを明確にしておかなければ、必要な準備や対応手順が曖昧になり、現場が混乱する原因になってしまうからです。
特に医療機関では、地域や立地条件によって直面するリスクが異なるため、自院に特有のリスクを可視化しなければなりません。
例えば、以下のような観点から被害を想定しておくと効果的です。
- 地震や豪雨など、地域特有の災害リスク
- 医薬品や備品などの物流の停止
- 通信や電力の遮断による情報伝達の遅延
- 医療従事者の出勤困難や患者の急増
- 高齢者や要配慮者の安全確保が困難になるケース
地域の人口構成や通院患者の属性(高齢者が多い、慢性疾患の患者が多いなど)も踏まえることで、より現実的なシナリオを描くことができます。
優先して維持すべき業務を選定する
非常時には、すべての業務を通常通りに実施するのは困難なため、あらかじめ「継続すべき業務」と「一時的に停止できる業務」を整理し、優先順位を明確にしておく必要があります。
限られた人員や資源の中で適切に判断・対応するには「何が命に直結するか」「地域医療において欠かせない機能は何か」を見極めておくことが大切です。
例えば、以下のような業務は優先度が高く設定されやすいものです。
- 救急診療や重症患者への対応
- 感染症対応やトリアージの体制
- 電源・通信など医療インフラの維持
- 在宅患者や高齢者施設への支援継続
上記のような業務については、必要なスタッフや設備、資材を事前に洗い出し、限られたリソースでも実行可能なレベルにまで落とし込んだ対応計画が求められます。
BCPにおいては「全てを守る」ではなく「何を優先して守るか」を決めておくことが、実効性のある対策に直結します。
中小病院・クリニックでもできる
BCP運用のポイント
BCPは大規模な医療機関だけの取り組みに思われがちですが、中小病院やクリニックでも、規模に応じた備えを進めることが十分に可能です。
限られた人員・設備の中でも、工夫次第で現実的なBCP運用が実現できるでしょう。
ここでは、中小規模の医療機関でも取り組みやすいBCPの実践ポイントを紹介します。
無理のない範囲で、日々の業務とBCPをどうつなげていくかを、順を追って具体的に見ていきましょう。
既存業務と連携させる
BCPは、日常業務と分けて考えるのではなく、普段の業務の中に組み込むことで、より現実的に機能します。
中小規模の医療機関では特に、限られた人員で対応しなければならないため、いつも使っているシステムや業務手順にBCPの視点を加える工夫が大切です。
例えば、以下のような「既存業務とBCPの接点」を整理しておくと、非常時にも慌てずに対応できるでしょう。
| 項目 | 通常業務 | 非常時のBCP対応例 |
|---|---|---|
| レセプト請求 | 電子レセプトシステム | 電源喪失に備え、手書き様式を準備 |
| 電子カルテ | クラウド型または院内サーバー | 定期的なバックアップ+電源確保 |
| 電話対応 | 院内の固定電話 | モバイル回線・緊急連絡先リストの整備 |
| 情報管理 | デジタルデータ中心 | 紙ベースでの最低限の記録フォーマットも用意 |
日々の業務とつなげて考えることで「災害時だけの特別な対応」ではなく、現場で自然に運用できるBCPが実現できます。
職員へ周知を進める
BCPの内容を職員全員にしっかりと理解・共有しておくことは、緊急時に機能する体制を構築するうえで欠かせません。
BCPをどれだけ綿密に作っても、現場の職員が「知らない」「覚えていない」状態では、非常時に動けず、混乱や対応の遅れにつながります。
特に中小病院やクリニックでは、少人数体制での対応が求められるため、一人ひとりが自分の役割を把握しておかなければなりません。
例えば、BCPの周知には以下のような工夫が有効です。
- 朝礼の時間を活用してポイントを繰り返し伝える
- 院内掲示板に要点を掲示する
- 定期的なミニ研修やロールプレイ形式で実施内容を体験してもらう
上記のように、伝えるだけでなく身につけてもらう工夫が求められます。
BCPは「職員が理解し、行動できてはじめて意味を持つ計画」です。
だからこそ、マニュアルの配布だけで終わらせず、理解と定着を意識した継続的な周知活動が大切です。
定期的に訓練を実施する
BCPを実際に機能させるには、計画を立てるだけではなく、定期的な訓練を通じて現場で動ける形にしておくことが欠かせません。
医療機関では、避難誘導や安否確認、診療の継続など多くの動作が同時並行で求められるため、あらかじめ訓練しておくことで混乱や判断ミスを最小限に抑えられます。
訓練を通じて初めて見える課題や連携ミスもわかり、計画の見直しにもつながるでしょう。
例えば、次のようなシチュエーションを想定した訓練を取り入れることで、より実践的な対応力が身につきます。
- 外来診療中に大規模な地震が発生
- 夜間に院内の停電と通信障害が発生
- 職員の半数が感染症で出勤できない
- 入院患者の一部を他施設へ搬送する必要が出た
訓練では、具体的な状況をもとに、役割行動や連絡手順のシミュレーションを実施する必要があります。
BCPは訓練を通じてこそ「動ける計画」になります。
年に1~2回は実施し、内容を更新しながら継続的に精度を高めていきましょう。
ITツールを活用する
BCPを現場で無理なく運用するためには、ITツールの活用が効果的です。
アナログ管理に頼っていると、備蓄のチェックや職員への連絡、安否確認などの対応が煩雑になりやすく、いざというときに情報が行き届かなかったり、対応が遅れるリスクが高まります。
特に中小規模の医療機関では、少人数で対応しなければならないため、人手に頼らずに動く仕組みが求められます。
例えば、以下のようなBCP業務にITツールを導入すれば、日常管理と非常時対応の両面で効率化が図れるでしょう。
- 備蓄物資の在庫管理や使用期限のチェック
- 安否確認や職員間の連絡体制の整備
- 院内での情報共有や対応マニュアルの電子化
- 発災時の対応状況を一元管理するダッシュボード
ITツールは「BCPの実行力」を高めてくれるツールです。
紙や口頭に頼る運用から、ツールを活用した「見える・届く・動ける」体制へ移行する必要があります。
クロスゼロを活用した
BCP運用の効率化
ここまで、BCPを策定・運用するための基本的な考え方や中小医療機関での実践ポイントを紹介してきました。
とはいえ、実際の現場では「人手が足りない」「管理が煩雑」といった課題に直面する場合も少なくありません。
そこでおすすめなのが、BCP運用を支援するITツール「クロスゼロ」です。
クロスゼロは、安否確認や備蓄管理、情報共有など、BCPに必要な要素をひとつのシステムに集約し、現場の負担を軽減するクラウドサービスです。
ここでは以下の内容について紹介します。
実際の利用シーンを通して、自院の運用に活用できるか確認してみてください。
クロスゼロとは?
クロスゼロは、日常から非常時まで一貫して使える、総合防災アプリです。
さまざまな現場で防災対策を進める上で「安否確認」「備蓄管理」「情報共有」など、BCPの実務を効率化・可視化する仕組みが求められています。
クロスゼロは、そうした現場の課題に役立つ機能を備える、総合防災アプリです。
例えば、クロスゼロは次のような用途に活用できます。
- 平時は備蓄のチェックや避難所情報の共有など、日常業務と連携
- 災害時は自動で安否確認を配信、職員や家族の状況を即時に把握
- 気象庁の情報やSNS由来の災害情報をAIで収集し、迅速に共有
- ファイル共有・マニュアル管理機能により、BCP文書の電子化も可能
クロスゼロは、単なる安否確認アプリではなく、BCPを「実行できる計画」にするためのプラットフォームとして、多くの現場で活用が進んでいます。
「クロスゼロ」でできること
クロスゼロでは、以下のような機能を備えています。
| 安否確認 | 災害発生時に自動でメッセージを配信し、職員や家族の状況を即時に把握 |
|---|---|
| 備蓄管理 | 在庫数や使用期限をデジタルで一括管理。棚卸しや入れ替えも簡単 |
| 情報共有 | 災害情報や対応マニュアルを関係者にリアルタイムで共有 |
| ファイル管理 | 避難指示書・手順書などを電子ファイルとして保存・配信 |
| 多拠点管理 | 複数施設の状況を一括で確認・対応 |
| 防災訓練支援 | 訓練ログを記録し、BCPの継続的な改善に活用できる |
クロスゼロは「日常から災害時まで切れ目なく使える」設計で、BCP運用の効率化と現場の安心感を両立させるツールです。
実際の導入事例「特別養護老人ホームはまなす苑」
クロスゼロは、災害対策だけではなく、日常業務の中でも使える防災ツールとして、高齢者福祉施設でも実践的に活用されています。
特別養護老人ホームはまなす苑(兵庫県豊岡市)では、これまで災害時の安否確認や連絡手段に課題があり、BCPの実効性に不安を抱えていました。
特に2024年の能登半島地震の際には、津波警報の発令により外国人スタッフの避難がスムーズにできなかった経験から「伝える手段の限界」を痛感したそうです。
導入後は、以下のような改善が見られました。
- 災害発生時に、安否確認を即時に送信できる体制を整備
- 業務用チャット機能により、職員間の連絡が一元化
- 緊急避難場所の共有や、マニュアル・シフト表のデジタル管理が可能に
- 平時からの活用で、災害時も自然に使える体制を構築
現在は、スタッフ約76名がクロスゼロを活用しており、チャットやファイル共有も日常的に行われています。
「防災=非常時だけ」ではなく「業務の中で自然に使う防災」が実現されつつある事例です。
まとめ
医療機関にとってBCPは「非常時に命を守る」ための備えです。
災害や感染症など、想定されるリスクに応じた体制づくりを進めておくことで、非常時にも診療を継続し、地域医療を支えることができます。
中小病院やクリニックでも、日常業務と連携したBCPの運用や、ITツールを活用した効率化が可能です。
まずは自院の状況を見直し、できるところから取り組んでみてください。
なお記事内で紹介した「クロスゼロ」では、30日間の無料体験や資料請求も受け付けています。
BCPの一歩を踏み出すツールとして、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
災害発生時は“最初の1分”で差がつきます。
総合防災アプリ「クロスゼロ」なら、気象庁情報に連動した通知と安否確認を自動で配信。初動の遅れを最小にします。避難指示や連絡を即座に届け、防災対策をもっと効率的に。
クロスゼロの機能や導入事例をまとめた資料を無料でご用意しました。
役立つ情報満載
クロスゼロに関する
無料相談(最大60分)
総合防災アプリ「クロスゼロ」にご興味をお持ちいただいた方は、お気軽にお申し込みください。
企業防災の仕組みづくりや防災DXに関するご相談はもちろん、ご希望がございましたら「クロスゼロ」の機能をご覧いただくこともできます。