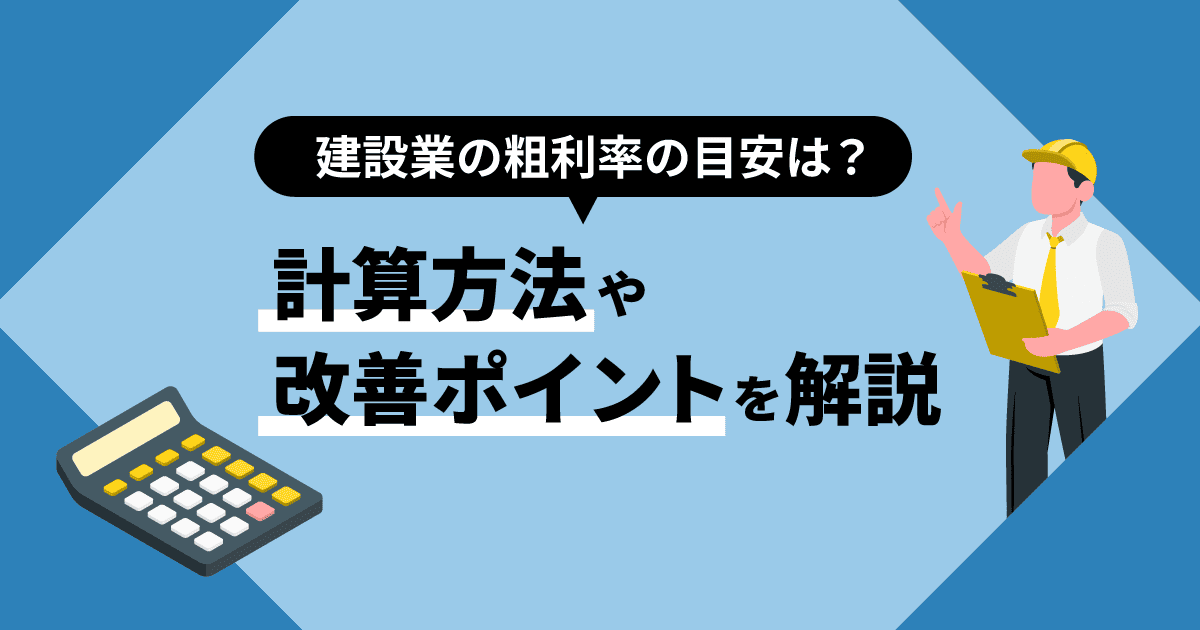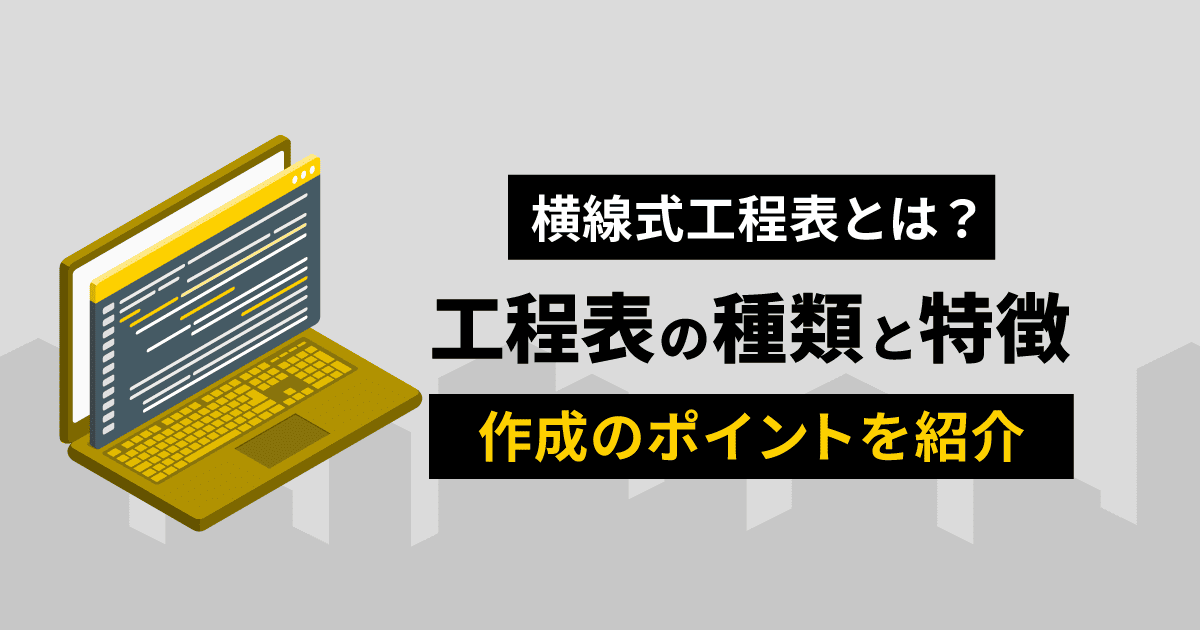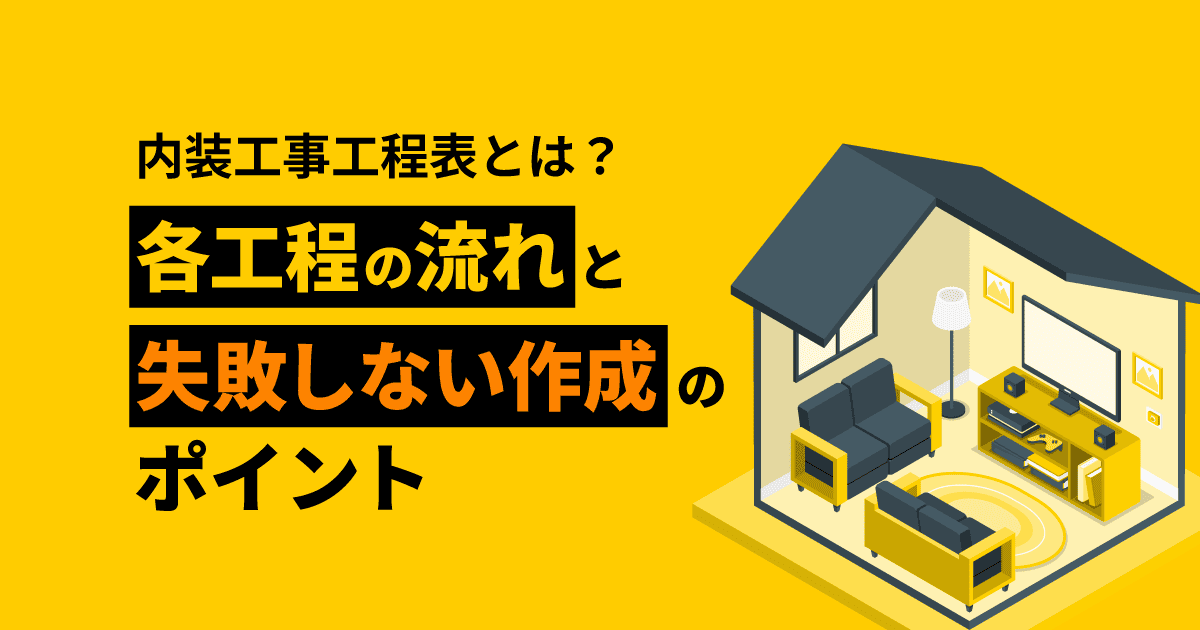【建設業の経営改善】社内の仕組みを改善し、利益率を高める方法を解説
2025/6/17
案件が順調に増え、売上も上がっているのに利益がなかなか上がらない。そんな悩みを抱えてはいないでしょうか。
特に小規模の建設企業で、急に案件が増え始めた頃に起こりがちな悩みです。この状況は情報共有が上手くいっておらず、お金の流れを把握する仕組みが整っていないことによって引き起こされているのかもしれません。
本記事ではそんなお悩みを解消するために、利益率が低くなってしまっている原因や利益率が高い会社の特徴、利益率を高める方法について解説します。
もくじ
建設業界における
平均的な利益率は25%
建設業情報管理センターが公開している令和5年度の「建設業の経営分析」によると、建設業全体の粗利益率(総売上高総利益率)の平均値は25.95%です。粗利益率は企業の収益性や経営効率を確認することができる指標で、(売上総利益÷総売上高)×100で求められます。

グラフからは土木建築業は平均18.05%、建築業は平均19.64%など同じ建設業の中でも平均の利益率に差があることが分かります。そのため、平均的な利益率は25%と言っても、適正な利益率は18〜25%程度と考えておくのが良いでしょう。
また、国土交通省が公開している令和3年のデータによると、測量業の平均値は52.7%、地質調査業39.2%であり、建設業は他の業界に比べると粗利益率は低水準となっています。建設業は高額な代金の工事を請け負うものの、長期にわたる施工期間や必要な人手・材料などの多さ、専門性が必要となるための多重下請け構造など、工事代金も高額です。
参考:国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 専門工事業・建設関連業振興室「建設関連業の経営分析(令和3年度)」
利益率が低い原因・理由
適正な値よりも利益率が下回っている場合の主な原因について解説します。
当然ですが、売上額が低いと利益率は下がります。しかし、売上額を上げるためには、「発注数」や「単価」などを上げる必要があり、自社の取り組みだけですぐに改善できるものではありません。よって今回は、社内に目を向け改善できるポイントに絞って解説します。
原価管理ができていない
原価管理ができていないと適切な原価になっているか把握できず、気づけば原価率が高くなってしまっていたということになりがちです。利益をしっかりと出せる原価になっているか、小まめに管理することが大切です。
また、原価管理を行うことはコストの削減にもつながります。資材の発注などを現場に任せきりにしていると、材料の過剰発注によって気づかないうちに適正な原価率を超えてしまうこともあり得ます。原価管理によって適切な材料の発注量になっているか確認し、不要な原価発生を抑えましょう。
お金の流れが把握できる仕組みが整っていない
お金の流れが把握できる仕組みが整っていないと、費用発生の内訳も分からず有効なお金の使い方をできているのか検証できないため、利益率はなかなか上がりません。
どこの現場で何のための費用が発生しているのか把握できなければ、無駄な費用が発生しているかどうかも分からないままです。現場、内容、使用している人物など、費用が発生するポイントはどこかきちんと把握できるようにしましょう。
「経営者が現場に関わるお金の状況が分からない」という状態にしないためにも、予算を作成する・発注状況をチェックするなどお金に関わる一連の流れが把握できる仕組みにしましょう。
お金に関わる一連の流れが把握できるように、情報共有をスムーズにできる方法を考えるのも大切です。
利益率が高い建設業の特徴とは
利益率が高い企業は、お金の流れを把握できる仕組み化ができている企業です。お金の流れを把握できれば利益を試算することが容易になり、利益率を上げることができます。
ここで、利益率の改善に成功した企業の事例をひとつご紹介します。
情報共有の仕組みを改善し利益率を改善したK社の事例
K社は小規模な建設業者で、会社の急成長に伴い「売上は増えるのに利益が増えない」という課題に直面していました。そこで、情報共有の仕組みを根本から改善し、お金の流れを把握できるようにすることで利益率の改善に成功したのです。
特に従業員数が少なく、利益率を「何とかしたいけど何にもできない」と悩んでいる小規模な建設業者の方に向けて参考になる事例と言えます。
利益率を高める方法
次に、具体的に利益率を高める方法についてご紹介します。
資材の過剰発注を見直す
まずは資材の過剰発注を見直すことです。「大は小を兼ねる」という言葉があるように、人間の心理として選べるのであれば過剰に発注しがちです。もちろん何かあったときの予備だったり追加発注の手間を減らしたりといった理由もあるかと思いますが、全てに過剰発注をしていて原価率は上がる一方です。
何かあったときの予備の資材は別でストックしておき、それぞれの工事では過剰に発注しないようにするなど、過剰発注を減らすための対策を取ると良いでしょう。
お金の流れが把握できる仕組みを構築する
お金の流れを把握できる仕組みを整えることで、どこにどれだけお金を使用しているのか分かるようになり、改善の余地にも気づけるようになります。
個人個人の裁量に任せるのも大事ですが、良かれと思ってやっていたことが利益率を下げる原因である可能性もあります。お金の流れを簡単に把握できる仕組みを整え、意図しないお金が発生していないかなど、すぐに気づけるようにしましょう。
「PROSHARE」を活用して
お金の流れを把握できる
仕組みを作ろう
先ほどご紹介した利益率の改善した会社の事例では、情報共有ツール「PROSHARE」を上手く活用することでお金の流れが把握できるような仕組みを整えていました。同規模の企業であれば非常に再現性の高い取り組みですので、ぜひ参考にしてみてください。
ポイントはPROSHAREのチャット機能です。チャットを使って現場とスムーズにコミュニケーションを取れるようにすることで、各現場の原価率や使用材料の把握ができるようになりました。現場の状況を把握することで進捗確認や材料を使用しすぎていないか確認したり、原価管理がしやすくなったりと、利益率の改善につながったのです
またPROSHAREはチャット機能の他にも、現場の情報を一元管理できる案件管理機能、社内だけでなく協力会社とも使えるスケジュール機能が備わっています。必要最小限の機能でシンプル設計のため、導入の際のコストも抑えられるのも特徴です。
▼詳しい情報はこちらから
建設業向け情報共有ツール「PROSHARE(プロシェア)」
「PROSHARE(プロシェア)」導入による成功事例
まとめ
本記事では、建設業界の利益率が低い原因と、利益率が高い企業の特徴、利益率を高める方法について解説しました。
社内で利益率が低くなってしまっている原因を突き詰めていくと、情報共有の問題につながっていることが多いのではないでしょうか。情報共有は一見簡単なことに思えますが、必要な情報をストレスなくスムーズにやり取りすることはなかなか難しいことです。社内外のコミュニケーションを円滑にし、情報共有から派生する問題を改善するためにも、ツールを上手く取り入れてみてはいかがでしょうか。
情報共有の問題を解決すると、利益率の改善の他に業務効率化にもつながります。情報共有ツール「PROSHARE」は建設業界に特化した機能を厳選しているため、簡単でシンプルな操作性となっています。
PROSHAREに関する
無料相談(最大90分)
建築現場向け情報共有ツール「PROSHARE」にご興味をお持ちいただいた方は、お気軽にお申し込みください。
業務効率化に関するご相談はもちろん、ご希望がございましたらPROSHARE の機能をご覧いただくこともできます。